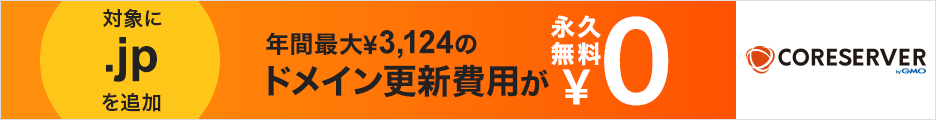食べ物でニキビを治そう!ニキビの予防&改善に効果的な栄養素と食事
肌の調子と食生活は大いに関連があります。ニキビや吹き出物が出やすい人は、食生活に少し問題があるのかもしれません。
今回はニキビや吹き出物ができやすい人に重点的に摂取してほしい栄養素、ニキビや吹き出物の予防・改善におすすめの食べ物などを紹介したいと思います。
化粧品や薬を使っても治りが悪いと感じている人は、食生活を見直して体の内側からニキビや吹き出物を改善していきましょう。
ニキビや吹き出物に効く栄養素はビタミンB2・C・B6
思春期に出るニキビ、ストレスやホルモンバランスの乱れで出る吹き出物(大人ニキビ)は、毛穴に皮脂が詰まって炎症が起こる慢性の皮膚疾患です。
一般的なケアは、ニキビ用の化粧品を使った肌の手入れや外用薬での治療です。そして「肌にいい」「ニキビに効く」と言われ、サプリメントを飲んだり、その栄養素が多く含まれる食品を食べてみたりする人も多いのではないでしょうか。
- ビタミンB2
- ビタミンC
- ビタミンB6
この3つは、食品を幅広く組み合わせ主食とおかずのバランスが良い食事をとっていれば不足しにくい栄養素です。
ただし、食事が不規則だったり食事内容に偏りがあったりするとどれかが不足し、肌の機能が低下してニキビや吹き出物が出やすくなってしまいます。
まずは、それぞれの栄養素の生理作用と効率の良い摂取の仕方を説明していきたいと思います。
重要!皮脂の分泌を抑え毛穴の詰まりを防ぐビタミンB2
ビタミンB2は、ニキビや吹き出物が出やすい人にとっては特に重要な栄養素です。
ビタミンB2は、ニキビの原因となる「皮脂の過剰分泌」を抑えることで、毛穴が皮脂でふさがってニキビに発展してしまうのを防ぎます。
ビタミンB2の生理作用
ビタミンB2は主に脂質の代謝に関与する栄養素です。
代謝とは栄養素を分解してエネルギーに替えるはたらきのことで、代謝によって生まれるエネルギーによって体の機能がスムーズに動き、皮膚もすこやかに保たれます。
ビタミンB2が十分にあると脂質が余ることなくエネルギーに作り替えられるので、余った脂質が体脂肪や皮脂に変わってしまうのを防ぐことにつながります。
B2は代謝の際に補酵素(酵素を助ける物質)に変わることで、体のあらゆる機能のはたらきも助けています。
ビタミンB2は、特に補酵素としてたんぱく質から細胞を作り体を成長させる役割があるため、growth(成長)のビタミン(ビタミンG)とも呼ばれていました。
するとターンオーバーによって毛穴の角栓(皮脂や老廃物)がスムーズに排出されるので、毛穴が詰まりにくくなります。
またニキビや吹き出物ができたとしてもすぐに新しい皮膚が生え替わってくるので、早くキレイに治しやすくなるのです。
もしもビタミンB2が不足すると、脂質がスムーズに代謝されなくなるので、皮脂の分泌が過剰になってニキビや吹き出物、脂漏性湿疹が起こりやすくなってしまいます。
またターンオーバーの異常により肌荒れ、口角炎、舌炎など皮膚や粘膜の炎症も起こりやすくなります。
ビタミンB2を摂取するには
ビタミンB2はしっかり摂取しなければなりませんが、幅広い食品に含まれているので、通常の食生活を送っていれば不足する心配はいらない栄養素です。
肉、魚、乳製品、卵・豆類の摂取を特に控えていない人は、簡単に補給することができます。
食事摂取基準では、成人の男性で1日に1.6mg程度、女性で1.2mg程度のビタミンB2を摂取することが推奨されています。
そして、15~17歳の男子は1.7mg、12~17歳の女子は1.4mgと、成長期でニキビも出やすい世代は、より多くのビタミンB2が必要となっています。
ビタミンB2は水溶性で尿と一緒に排出されやすく、食事から多めに摂取しても過剰摂取になる心配はありません。
ビタミンB2を多く含む主な食品と1食分の含有量の一例を紹介します。
| 食品名 | ビタミンB2含有量(mg) |
|---|---|
| 豚レバー(80g) | 2.88 |
| ウナギのかば焼き(1串100g) | 0.75 |
| カレイ(小1尾100g) | 0.35 |
| 納豆(1パック40g) | 0.24 |
| うずら玉子(3個30g) | 0.22 |
| カマンベルチーズ(1ピース20g) | 0.10 |
| アボカド(1/2個50g) | 0.10 |
参照…食品成分表2015(女子栄養大学出版部)
ビタミンB2を摂取する時のポイント
ビタミンB2は食事から取り込みやすい栄養素ですが調理で損失されやすいので、ニキビや吹き出物対策のためには多めに摂取するのがおすすめです。
特に脂質の摂取量が多い人はビタミンB2は体内で消費されやすいので、ビタミンB2が足りなくなって皮脂の分泌量が増えてしまうことがあります。油分が多い物をよく食べる人は意識してビタミンB2も多く摂取しましょう。
お酒と一緒に摂取するのは控えましょう。アルコールを処理する段階でビタミンB2が消耗され、皮脂の過剰分泌につながります。
美肌に効くビタミンの代表選手ビタミンC
ビタミンB2の次に積極的な摂取をおすすめしたいのが、ビタミンCです。
ビタミンCは美肌に良いビタミンの代表選手。丈夫な皮膚や粘膜を生成し皮膚の炎症を早くキレイに治す働きを持っています。
ニキビや吹き出物の改善に効果が期待され、ニキビ用の外用薬や化粧品にも配合されています。体の内側から摂取するビタミンCは、肌からしみこむビタミンCとはまた違ったアプローチでニキビや吹き出物を改善していきます。
ビタミンの生理作用
ビタミンCはさまざまな生理作用があり、生命の維持には欠かすことのない栄養素です。
その中でニキビや吹き出物に関連する作用を挙げると、まずコラーゲンの生成に欠かせないところが大きな特徴となります。
コラーゲンは、細胞と細胞の間のすき間を埋めるクッションの役割をしていて、皮膚、内臓、血管、骨などあらゆる場所に存在しています。
コラーゲンがスムーズに生成されていれば、新しい皮膚の成長が促進されるので傷ができても治りが早くなります。皮膚トラブルの治療にはビタミンCの内服薬や外用薬を組み合わせることもあります。
また、ビタミンCが持つ「皮膚の美白作用」も有名な作用です。
ビタミンCは皮膚に色素が沈着する原因「メラニン」の生成を抑制したり、できてしまったメラニンを漂白する作用があります。ビタミンCを摂取すると、炎症が起きた部分に色素が沈着するのを防ぎ跡が残りにくくなる効果が期待できます。
皮脂の過剰分泌の原因のひとつにストレスがあります。ビタミンCはそのストレスに対抗する力も高めてくれます。
ストレスを受けると、男女とも交感神経の影響で皮脂の分泌を促進する男性ホルモンの分泌量が増えてしまいます。
ストレスと皮脂は関連性がないようにも見えますが、実は意外と大きな影響をもたらしていて、ストレス対策にビタミンCをしっかり摂取することがニキビや吹き出物対策につながっています。
またビタミンCには鉄の吸収率を高める作用もあります。
鉄から赤血球のヘモグロビンが作られ、酸素を皮膚細胞に運ぶ量が増えると、ターンオーバーがスムーズになります。鉄が欠乏しやすい女性は、ビタミンCと鉄を積極的に摂取することがニキビや吹き出物の予防にもつながることになります。
ビタミンCを摂取するには
食事摂取基準では、15歳以上で1日に100mgのビタミンCを摂取することが推奨されています。
しかし、厚生労働省による平成26年国民健康・栄養調査報告では、15歳以上の男女の1日あたりの摂取量平均値が推奨量を下回る70mg前後と報告されていて、日本人にはビタミンCが不足しやすい傾向がうかがえます。
ビタミンCは野菜・果物全般に含まれるほか、機能性食品や保存料(抗酸化剤)として加工食品によく使われています。
野菜や果物をしっかり食べていれば補給は難しくない栄養素なのですが、若い人を中心に野菜不足や果物離れの人が増えてきているので、ビタミンCが不足しやすいようです。
ニキビや吹き出物を治したい人は、意識してビタミンCの多い野菜や果物を毎日食べるようにしたいですね。
ビタミンCを多く含む主な食品と1食分の含有量の一例を紹介します。
| 食品名 | ビタミンC含有量(mg) |
|---|---|
| 赤ピーマン(1/2個60g) | 102 |
| 柿(1個120g) | 84 |
| ブッコリー(1/4個60g) | 72 |
| オレンジ(1個135g) | 54 |
| いちご(5個75g) | 47 |
| ピーマン(1個50g) | 38 |
| じゃがいも(1個120g) | 35 |
ビタミンCを摂取する時のポイント
ビタミンCは水に溶けやすく熱に弱いので、ゆでたり煮たりするとビタミンCが損失されてしまいます。
そこで効率良く摂取するなら、生で食べられるものを選ぶのが一番おすすめです。また、じゃがいもはデンプンがビタミンCの流出を防ぎ、加熱してもビタミンCが損失されにくいといわれています。
ビタミンCは消耗されやすく尿と一緒に排出されやすいので、意識して摂取しないとすぐに不足してしまいます。過剰摂取が起こりにくい栄養素なので、食事からビタミンCを多めに摂取してもかまいません。
また取り溜めはできない栄養素なので、3時間おきくらいに少量ずつこまめに摂取すると効果が発揮されやすくなります。間食にはビタミンCたっぷりのフレッシュジュースもおすすめです。
ビタミンCが十分に摂取できていれば、病気にかかりにくくなる、シミやしわなどの肌トラブルも改善される、といった嬉しいオマケもついてきます。
ビタミンB2と一緒に摂取したいビタミンB6
ビタミンB6は、ビタミンB2と同様に補酵素としてはたらき、その作用のひとつに丈夫な皮膚や粘膜を作る役割があります。
ビタミンB2とは同じビタミンB郡として助け合う関係でもあり、どちらも皮膚や粘膜を作る役割があることから、ビタミンB2・B6を一緒に摂取すればニキビや吹き出物を予防・治療する効果がさらにアップします。
ビタミンB6の生理作用
ビタミンB6は、主にたんぱく質の代謝に関与している栄養素です。
また、女性ホルモンのバランスを整える作用があるので、女性の体で男性ホルモンの分泌が増え過ぎるのを抑え、皮脂が過剰に分泌するのを防いでくれます。
そのため、ホルモンバランスの乱れで起こる月経前症候群や大人ニキビの症状を緩和する効果も期待されます。
ビタミンB6を摂取するには
ビタミンB6は幅広い食品から摂取でき、体内でも腸内細菌によって生成されるため、通常の食生活を送っていれば不足することはめったにありません。
ただし妊娠、薬(ピルや抗生物質)の服用などの影響で腸内細菌のバランスが乱れるとビタミンB6が欠乏し、ニキビや吹き出物、脂漏性湿疹、肌荒れ、舌炎といった皮膚や粘膜の炎症が起こりやすくなります。
食事摂取基準では、成人の男性で1日に1.4mg、女性で1.2mgのビタミンB6を摂取することが推奨されています。
15~17歳の男子は1.5mg、12~17歳の女子は1.3mgと、思春期にはより多くのビタミンB6が必要です。
ビタミンB6を多く含む主な食品と1食分の含有量の一例を紹介します。
| 食品名 | ビタミンB2含有量(mg) |
|---|---|
| マグロ(刺身6切れ80g) | 0.86 |
| 牛レバー(80g) | 0.71 |
| 鶏ささみ(2本80g) | 0.53 |
| 玄米ご飯(1膳140g) | 0.29 |
| にんにく(10g) | 0.15 |
| 納豆(1パック40g) | 0.10 |
ビタミンB6は水溶性で尿と一緒に排出されやすく、食事から多めに摂取する程度では過剰摂取になる心配はありません。
不足しないように摂取したいニキビ・吹き出物に効く栄養素
ニキビ・吹き出物の出やすい人は、ビタミンB2・C・B6のほかにビタミンA・ビタミンE・亜鉛・食物繊維・パントテン酸も積極的に摂取しましょう。
ニキビ・吹き出物に効く「ビタミンA」
ビタミンAは皮膚や粘膜を健やかに保つ栄養素です。
- ビタミンAの効能
- 皮膚の乾燥を防ぐことで皮脂の分泌が過剰になるのを抑える
- ターンオーバーを促進し、ニキビや吹き出物を早くキレイに治す
- 抗酸化作用により、ニキビの原因となる皮脂の酸化を防ぐ
食品から摂取できるビタミンAにはいくつかの種類があり、そのほとんどは「レチノール」とビタミンAの前駆体で植物性の「β-カロテン」です。
レチノールは肝臓の脂肪や体脂肪に溶けて蓄積されやすく過剰症が起こりやすいのですが、β-カロテンは体に入ってから必要な分だけビタミンAに変換されるので大量に摂取しても過剰症にはなりません。
ビタミンAを摂取するならなるべくβ-カロテンを摂取するのがおすすめです。レチノールは動物性食品、βカロテンは植物性食品に含まれています。サプリメントの常用はビタミンAが体内に蓄積されやすいので、食事から摂取することをおすすめします。
- レチノールの多い食品
- レバー
- ウナギのかば焼き
- バター
- βカロテンの多い食品
- にんじん
- モロヘイヤ
- かぼちゃ
- みかん
βカロテンは緑黄色野菜や果物に多く含まれています。またビタミンAは油と一緒に摂取すると吸収されやすいので、調理をするならば油で炒めたりドレッシングをかけて食べるのが効果的です。
ニキビ・吹き出物に効く「ビタミンE」
ビタミンEは皮膚をすこやかに保つ作用のある栄養素です。
- ビタミンEの効能
- 血行を促進して皮膚細胞に栄養を与え、皮膚のターンオーバーを促進させる
- ホルモンバランスを整えることで皮脂の過剰分泌を抑制する
- 抗酸化作用により、ニキビの原因となる皮脂の酸化を防ぐ
ビタミンEはビタミンAと同じ脂溶性ビタミンで体に吸収されやすいのですが過剰症はほとんど起こりません。
ビタミンEは「生殖ホルモン」とも呼ばれ、ホルモンを正常に分泌するために欠かせない栄養素です。大人ニキビの出やすい女性はビタミンEをしっかり摂取してホルモンバランスを整えましょう。
- ビタミンEの多い食品
- アーモンド
- ウナギのかば焼き
- バター
- にんじん
- モロヘイヤ
- かぼちゃ
- モロヘイヤ
- アボカド
ニキビ・吹き出物に効く「亜鉛」
亜鉛は細胞の新陳代謝に欠かせない栄養素です。
- 亜鉛の効能
- 新しい皮膚細胞を作り皮膚のターンオーバーを促進させる
- ホルモンバランスを整え皮脂の過剰分泌を抑制する
欠乏すると、皮膚の炎症のほか不妊症や味覚障害も起こりやすくなります。
通常の食事から摂取しにくいこともあり、食事で過剰症になる可能性はほとんどないといわれます。ただしサプリメントなどを常用するとまれに過剰症が起こるので、なるべく頑張って食事から摂取することをおすすめします。
- 亜鉛の多い食品
- 牡蠣
- レバー
- 牛肉
- かに
- 卵黄
- たらこ
ニキビ・吹き出物に効く「パントテン酸」
パントテン酸はビタミンB2・Cを助け、皮膚をすこやかに導く栄養素です。
- パントテン酸の効能
- ビタミンB2が脂質を代謝するのを助ける
- ビタミンCがコラーゲンを生成するのを助ける
- 皮脂の過剰分泌の原因となるストレスを緩和させる
「パントテン」は「どこにでもある、ありふれた」という意味があり、パントテン酸は身近な食品に幅広く含まれ通常の食生活で不足することはめったにありません。通常の食事で過剰症になる可能性はほとんどないといわれます。
ただしアルコールやカフェインの摂取で消耗されやすいので、アルコール、コーヒーなどをひんぱんに飲む人はパントテン酸の不足に注意が必要です。
- パントテン酸の多い食品
- レバー
- 卵黄
- 納豆
- 鶏肉
- アボカド
- ブロッコリー
ニキビ・吹き出物対策にオススメの食べ物・飲み物
肌に良い食品はたくさんありますが、その中でもニキビや吹き出物に良い栄養素がギュッと詰まった食品を選んでみました。
苦手なものもあるかもしれませんが、肌のためこれを機に食卓に挙げる機会を増やしていただけると嬉しいです。
ニキビ・吹き出物対策にオススメの食品:レバー
栄養の宝庫レバーは、特にビタミンA、ビタミンB群、ミネラルがたっぷり含まれ、ニキビや吹き出物の予防・改善にはもってこいの食品です。炒め物、煮物、揚げ物などさまざまなおかずにして食卓に取り入れましょう。
ただ、レチノールなど含有量が多すぎる栄養素もあるので、レバーの食べ過ぎには注意してください。
レバーは苦手な方もけっこう多いと思いますが、そんな方にもおすすめしたいのがレバー料理の中でも定番の「レバにら炒め」です。
にらもビタミンB群・Cが含まれ、肌に良い食品。レバにら炒めは調理しやすく、レバーが食べやすい形になっているのです。豚レバーでもおいしいですが、鶏レバーを使った基本のレバニラ炒めのレシピを紹介いたします。
土井善晴の初夏のおいしいもん「鶏レバにら」
材料(4人分)
・鶏レバー 200g
【下味】
・しょうゆ 大さじ1弱
・こしょう 適量
・かたくり粉 大さじ3
・にら 100g(1ワ)
・にんにく 1かけ
【合わせ調味料】
・しょうゆ 大さじ1/2
・砂糖 大さじ1/2
・酒 大さじ1
・サラダ油 大さじ2
・塩 小さじ1/3
- 鶏レバーは水けを拭いて、半分に切る。にらは食べやすく切り、サッと洗ってざるに上げておく。にんにくは粗みじん切りにする。【合わせ調味料】は混ぜ合わせておく。
- 鶏レバーに【下味】のしょうゆとこしょうをなじませたら、かたくり粉をまぶす。(なじむ程度でOK。もみ込む必要はない。)
- フライパンにサラダ油大さじ2、にんにくを強火で熱し、鶏レバーを並べ入れ、やや火を弱めて、両面を焼きつける。(油がかなりはねるので、フライパンのふたでガードしてやけどしないように注意する。)
- レバーに焼き色がついたら、一度全体を大きく返して、にらを加える。塩小さじ1/3をふり、【合わせ調味料】を回し入れ、ざっと混ぜて器に盛る。(にらは余分な火を入れないのがコツ。仕上げの塩で全体を引き締める。)
ニキビ・吹き出物対策にオススメの食品:ブロッコリー
ブロッコリーは値段が手ごろで身近な存在でありながら、β-カロテン、ビタミンC、ビタミンEが豊富なスーパー野菜です。
特に抗酸化作用を持つビタミンA・C・Eが揃って入っているところが肌に嬉しいです。
抗酸化作用を持つこれらのビタミンは、一緒に摂取することで互いの抗酸化作用を高め合う作用がはたらき、抗酸化作用がより強力になるのです。3つ併せて「ビタミンエース」とも呼ばれます。
ニキビや吹き出物を予防したい人はブロッコリーからビタミンエースを摂取して、皮脂の酸化を抑制しましょう。
ゆでてサラダで食べるのがシンプルでおいしいですが、チーズのビタミンB2も補給できる手軽なレシピを紹介したいと思います。
ブロッコリーのチーズ焼き
材料(2人分)分量のめやす
・ブロッコリー 100g
・トマトケチャップ 大さじ1
・ピザ用チーズ 40g
・こしょう 少々つくり方
- ブロッコリーは小房に分け、塩少々(分量外)を入れた熱湯でかためにゆでる。
- 耐熱容器に(1)を入れ、トマトケチャップをかけてこしょうをふり、チーズをちらす。
- オーブントースターでチーズに香ばしい焦げ目がつくまで5~6分焼く。
ニキビ・吹き出物対策にオススメの食品:赤ピーマン
赤ピーマン(パプリカ)は、特にビタミンCが豊富で、βカロテンやビタミンEもまとめて摂取できるところが魅力です。緑色のピーマンより苦味や臭みがないので、生のまま食べてビタミンCをしっかり摂取することができます。
抗酸化作用を持つ美肌成分「アスタキサンチン」と皮膚の材料となるたんぱく質を含む鮭を使ったレシピを紹介したいと思います。
鮭とパプリカのマリネ
材料(2人分)分量のめやす
・生鮭(切り身)2切れ
・塩 少々
・こしょう 少々
・小麦粉 適量
・パプリカ(黄) 1/2個
・パプリカ(赤) 1/2個
・玉ねぎ 1/2個
・サラダ油 大さじ2
・キッコーマン柚子の香り ゆずか(またはお好みのポン酢) 大さじ2つくり方
- 鮭はひと口大に切り、塩、こしょうで下味をつけ、小麦粉をはたく。
- パプリカは1cm幅のくし形に切り、斜め半分に切る。玉ねぎもくし形に切る。
- フライパンに油を温め、(1)を両面焼く。中まで火が入ったらバットに取り出し、ぽんずをかける。
- 同じフライパンで(2)を焼いて(3)に加え混ぜ、10分ほどおいて味をなじませる。
ニキビ・吹き出物対策にオススメの食品:鶏ささみ
鶏ささみは、皮膚の材料となるたんぱく質、ビタミンB6やパントテン酸を豊富に含みます。さらに脂質が少なくヘルシーなので、ニキビや吹き出物が出やすい人がお肉を食べたい時にピッタリな食品です。
味が淡白なので、一緒に組み合わせる食品にアクセントをつけると、よりおいしく楽しめますよ。ビタミンEが豊富なアーモンドを使った香ばしいレシピを紹介したいと思います。
ささ身のアーモンド衣焼き
材料(2人分)
・鶏ささ身 150g
A 酒 小さじ1
A 「瀬戸のほんじお」 少々
A 「味の素」 少々
・片栗粉 適量
・卵白 1個分
・スライスアーモンド 50g
・すだち 1個作り方
- ささ身はスジを取り、棒状に切り、Aをまぶして10~15分(時間外)おく。
- 水気を拭いた(1)のささ身に片栗粉を薄くまぶし、溶きほぐした卵白をつけ、アーモンドスライスをつける。
- オーブンシートを敷いた天板に(2)のささ身を並べ、オーブントースターで7~8分焼く。焦げるようなら、途中でアルミホイルをふんわりとかける。
- 器に盛り、すだち・焼き塩を添える。
ニキビ・吹き出物対策にオススメの飲み物:豆乳
ニキビ・吹き出物が出やすい人には豆乳をおすすめします。大豆の栄養が丸ごと入っている豆乳は、ビタミンB6やパントテン酸をはじめとするビタミンB群が含まれ、ビタミンEや女性ホルモンのバランスを整えるイソフラボンも摂取できます。
また肉や牛乳など動物性食品を控えている人の重要なたんぱく源になります。
そのまま飲むのも良いですし、オレンジやにんじんなどビタミンC、βカロテンを含む野菜や果物と一緒にスムージーにして飲むのもおすすめです。
ニキビ・吹き出物対策にオススメの飲み物:はと麦茶
はと麦茶は、イネ科の植物「はと麦」の実を煎じたお茶です。はと麦は「ヨクイニン」と呼ばれ、イボや肌荒れを治す漢方薬として知られます。
はと麦茶はアミノ酸、ビタミンB2、各種ミネラルなどが含まれ、味も良いので普段用のお茶として老若男女に親しまれています。ノンカフェインで体に優しいので、ニキビや吹き出物の出やすい人は水分補給も兼ねてはと麦茶を毎日飲むと良いでしょう。
肌の機能が低下する原因に…避けたい食生活とは
ニキビや吹き出物が出やすい人は、食生活に問題があるのかもしれません。次のような食生活には心当たりがありませんか。
- 皮膚に必要な栄養の不足を招く食生活
- 野菜や果物をほとんど食べない
- 食事はインスタントラーメンやカップめんで済ませることが多い
- 魚をほとんど食べない
- 皮脂の過剰分泌を招く食生活
- スナック菓子、ケーキ、ドーナツなど糖質と脂質が多い物が大好き
- 油っこい物が大好き
- 油を極端に控えている
- お酒をよく飲む
- 辛い物が大好き
- 1日に何杯もコーヒーを飲む
皮脂の過剰分泌を抑制し、ニキビや吹き出物を改善するには、上記のような食生活をやめて栄養バランスの良い規則正しい食生活に切り替えていきましょう。
バランスの良い食事にあわせ規則正しい生活習慣・十分な睡眠も
食品に薬のような即効性はないので、ニキビや吹き出物に良い食事を食べてすぐ効果があらわれるわけではありません。
肌のターンオーバーによって新しい皮膚に生まれ変わる28~40日後くらい(個人差があります)には肌の調子が良くなったと実感できるかと思います。
食事ではビタミンB2・B6・Cをはじめとする栄養素を不足なく摂取し、規則正しい生活習慣や十分な睡眠を心がけるようにして体調を整えることも大切です。
ニキビや吹き出物に悩まされなくなると鏡を見るのも楽しくなり、気持ちまで前向きに変わってくることでしょう。
その日が来るまで「この料理に入っているビタミン○は、皮膚のためにこんなはたらきをしてくれるんだ。」と栄養素に親しみを感じながら、バランスの良い食事をおいしく楽しく続けてくださると嬉しいです。